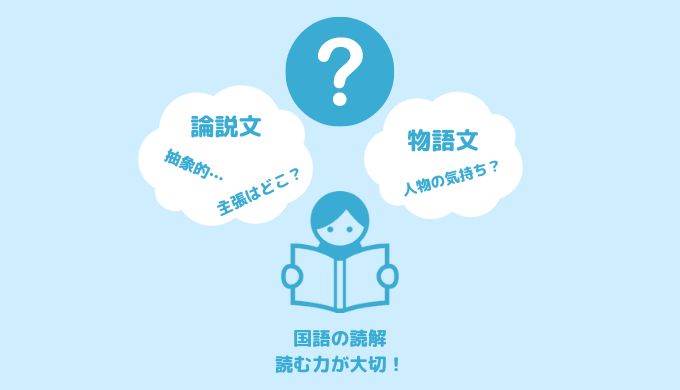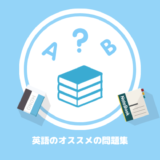「国語の点数はよいときと悪いときの差が大きくて……」
「勉強しているのに、国語の点数が伸びなくて……」
国語を苦手としている(または、得意とは言い切れない)子どもたちの多くは、上記のような不平や不満を口にします。
とくに、「物語文の問題はふつうに解けるけれど、説明文(論説文)はまったくダメで」とか、「国語の模試の点数が上がったり下がったりしてしまう」など、高得点をとれずに悩んでいる受験生は多くいらっしゃるでしょう。

国語の点数がアップしない、あるいは安定しないのはどうしてでしょうか?
今回の記事では、国語の点数を安定(アップ)する方法について解説します。
目次
国語の点数を安定(アップ)させるには?
入試における国語の問題は、漢字や文法(品詞など)の「知識」と、文章を読んで答える「読解」の2つにわけられます。
「読解」は「知識」問題に較べて配点が高いため、国語のテストで高得点をとるには、「文章をしっかりと読んで、問題に答える」力を養うことが大切です。
読解とは「読む」と「解く」こと
文章の「読解」とは読んで字のごとく、
- 読む
- 解く
この2つのことを指します。そして、先に挙げた「国語の点数が安定しない」受験生の多くは、2つのうちの「読む」ことをおろそかにしているケースがままあるのです。
「読む」力と「解く」力は、文章問題に取り組むうえでの両輪となるため、どちらが欠けても国語で高得点をとることはできません。
読むことは意外とおろそかに
塾に通っている小・中学生を見ていても、国語の成績が安定しない生徒さんほど、問題本文や設問文を読み飛ばしたり、思い込みで問題を解いてしまう傾向があります。
また、物語文よりも論説文を苦手としている受験生は、本文をしっかりと読めていない(内容を正確に理解していない)ことがあるので、注意をしましょう。
思い込みで解くのはNG!
問題をすぐに解き終わってしまう受験生に多いのが、「思い込みで解いてしまう」ことです。
例えば、物語文などで、似たようなストーリーをどこかで読んだことがあったり、自分がこれまでに経験したことと似ているエピソードがあると、本文をしっかりと読むことなく、「このときの主人公の気持ちは◯◯だ!」などと、勝手に思い込んで解答してしまうことがあります。
もし、みなさんにこのような傾向があるなら、国語の点数は安定しません。今すぐに本文や設問を読み飛ばすことなく、正確に読むよう心がけてください。
論説文は読む力がより大切!
文章をイメージしやすい物語文は解けるけれど、論説文(説明文)になるとまったく点をとれない場合にも注意が必要です。
論説文は抽象的なものが多いため、本文の内容をしっかりと理解せずに、ただ何となく目の前にある文字を読んでいる子どもたちを、塾の授業内においても多く見かけます。
論説文を筋道立てて理解するには、文に線を引いたり、接続語にマーキングしたりなどの作業をしながら読むことが大切です。
まずは、本文や設問の情報(条件)をしっかりととらえるために、文にマーキング(印付け)する習慣をつけるようにしましょう。
「読む」力とは?
「読む」力は、具体的に以下の3つにわけられます。
- 本文の内容を理解する力
- 内容を理解するための作業力
- 設問条件を理解する力
1〜3のなかでおろそかにされがちなのは「2」と「3」についてです。それでは、ひとつずつ解説していきましょう。
1. 本文の内容を理解する力
みなさんがふつうに想像する「読む」力とは、「本文の内容を理解する力」を指します。本文を理解するためには、語彙力、筋道立てて考える力、映像(物語文)や図式(説明文)としてイメージする力が必要です。
- 語彙力
- 論理的思考力
- 想像力
これら3つの力を伸ばすには、時間と手間がかかります。つまり、一朝一夕に効果(国語の点数がすぐにアップするなど)が現れにくいものです。学校・塾・家庭での学習をコツコツと行うことで、この3つの力は少しずつ伸びていきます。
多くの人がイメージする「読む」力とは、この「本文の内容を理解する」ことですが、国語のテストの得点を安定させるには、この力だけでは不十分です。
2. 内容を理解するための作業力
本文の内容を理解するためには、そこに書かれている情報をしっかりと整理する必要があります。このときに欠かせないのは、読みながら「作業」をすることです。この「作業」の手を抜くと、「わかったつもり」で問題を解くことになりかねません。
「作業」によって本文の内容をしっかりとつかむことができれば、問題を解くスピードと正確性が上がります。内容の理解は問題を解くうえでの大きなヒントとなるものですから、手を動かす「作業」も立派な読む力のひとつと言えます。

読むうえで、具体的にどのような作業をするのかは、後ほどくわしく説明します!
3. 設問条件を理解する力
問題本文だけではなく、設問についても、「抜き出し」なのか「説明しなさい」なのか、あるいは「本文中の言葉を用いて答えなさい」、「具体的に答えなさい」など、作問者の求める答えの条件をしっかりとチェックしなければなりません。
国語においては、作問者の求める答えを解答用紙に書かなければ「◯」にならないため、設問をしっかりと読む力もおろそかにはできないのです。
読む上での「作業」とはどのようなものか?
ここからは、「読む」力のひとつでもある「読むうえでの作業」について具体的に解説していきます。
先にも書いたように、みなさんは問題本文と設問のどちらにおいても「作業」をしなければなりません。それでは、どのような作業をすればよいのでしょうか?
問題本文の作業
中学・高校入試の問題文として出題されるのは、物語文、論説文(説明文)、随筆文の3つです。
今回はこのうちの物語文と論説文を読むうえでの作業についてお話しします。
物語文を読むときに、線を引いたり、マーキングをしたりするのは以下の3つです。
- 登場人物
- 人物の気持ち
- 気持ちが生じるきっかけとなったできごと
まず、登場人物は名前だけではなく、時代、住んでいる場所、年齢や家族構成、性格など、人物像(キャラクター)のわかる情報はすべて線を引いておきましょう。
次に、物語文の読解でよく問われるのが登場人物の「気持ち」なので、人物の心情(気持ち)について書かれていた場所を見つけたら必ずチェック(マーキング)してください。
また、「その気持ちになったのはなぜか?」と問われる問題もよく出題されるので、気持ちの変化の「きっかけ」となるできごとについてもチェックする必要があります。
論説文は以下の5つにマーキングをしましょう。
- テーマ(主題)
- 逆説の接続語
- まとめ言葉
- 傍線部のなかにある指示語
- 筆者の意見・主張
この5つについて、それぞれ細かく説明します。
1. テーマ(主題)
テーマ(または主題)とは、筆者がこれから説明するモノやコト、つまり「話題」です。テーマとなる言葉はキーワードとも呼ばれ、本文のなかでくり返し登場します。
くり返し出てくるキーワードや、筆者が説明したいと思っている「話題」を見つけたら、しっかりとチェックしておきましょう。
2. 逆説の接続語
逆説の接続語は、英語の長文読解だけではなく、国語においてもチェックが必須。なぜなら、筆者の述べたいことは逆説の「後ろ」に書かれているからです。
「筆者の述べたいこと=主張・意見」なので、論説文においては読み落としてはいけない部分となります。そのため、「だが、しかし、ところが、けれども」などの逆説の接続語を見つけたら、必ずマークをしましょう。
3. まとめ言葉
「まとめ言葉」とは、筆者の述べたい「まとめ=主張や意見」を導く言葉です。おもな「まとめ言葉」は以下の4つが挙げられます。
- このように(そのように)
- 要するに
- つまり
- すなわち
これらの言葉を見つけたら、逆説の接続語と同じようにマークし、その後ろに続く筆者の主張や意見にも線を引いておきましょう。
4. 傍線部のなかにある指示語
傍線部のなかにある指示語は必ずマーキングします。その理由を説明する前に、以下の例を見てください。
_線部①「でも、それって…」とありますが、なぜ主人公は言葉を続けられなかったのですか? ◯◯字以内で答えなさい。
【答え】
それを聞いた主人公が驚くとともに、かける言葉を見つけられなかったから。
もし、傍線部に「それ、これ、あれ」などの指示語がふくまれている場合、記述の解答ではその指示語をそのまま書いてはいけません。なぜかと言うと、解答者の書いた「それ」が作問者の解答と同じとはかぎらないからです。必ず、その指示語が示している内容をあきらかにしましょう。
これはしっかりとマーキングをしておけば防げるものなので、覚えておくようにしてください。
5. 筆者の意見・主張
筆者の主張・意見は、論説文のもっとも大切なところなので、見つけたら必ず線を引きます。主張や意見の探し方は、以下の4つを参考にしてください。
- 本文の最初と最後の意味段落
- 逆説の接続語
- まとめ言葉
- 「〜すべき」「〜する必要がある」などの文末
「逆説の接続語」と「まとめ言葉」にマークするときに、その後ろが主張や意見になってないかを気にしながら線を引くとよいでしょう。
設問の作業
設問文については、「何を」、「どのように」答えなければならないのかを、マーキングしながら確認します。例えば、以下のような設問文には注意が必要です。
_線部②「そのような理由」とありますが、どのようなことの理由ですか? 本文中から◯◯字で抜き出しなさい。
この問題は、「理由」を答えるのではなく、「理由の対象となること」を答えなければ正解になりません。とくに問題を解くスピードの速いお子さんほど、理由を答えてバツになってしまうケースをよく見ます。これも設問文をしっかりとチェックすれば防げるミスなので、取りこぼさないようにしましょう。
また、私立中学受験でよく出題される「脱文挿入問題」もミスをよく見かける問題のひとつです。これは本文から抜けている一文をもとにもどす問題なのですが、設問によっては「その一文が入る直前の五文字」あるいは「直後の五文字」と抜き出すところが異なるので、必ずチェックしてください。
読む力を高めよう!
読む力を高めると、国語の点数は安定します。
- 抽象的な論説文の内容を理解できる
- 自分の思い込みで問題を解かない
- 設問条件の見落としをしない
本文と設問文をしっかりと読むことによって、国語の点数は自然と高い水準で安定するはずです。
さいごに
国語の点数が安定しない、伸びないと悩んでいるのであれば、まずは読む力を高めるようにしましょう。
国語は正しい手順で「読む」と「解く」ことができれば、必ず点数の上がる科目です。「国語は苦手だから…」とあきらめることなく、むしろ得意科目となるように、まずは「読む」力を高めてください。